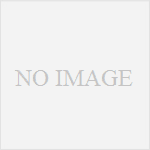山田のおやじは、基本的には厄年について気にしないという立場です。
それは、「何か悪いことが起きる年」ではないということであり、怖れる理由がないからです。
いろいろな文献を探してみますと、厄年をテーマにした本が出るのは1970年代に入ってからです。
「四十二歳は厄年か」(三笠書房 1972)、「厄の神秘」(白金書房 1974)、「厄年の科学」(光文社 1976)などが代表的なものであり、1970年になるまで、厄年に関する本は出ていないのです。
第二次大戦敗戦の日本では、自分たちが生きることに必死で、「厄年」なんてものに振り回される余裕がなかったからでしょうし、実際に厄年に「悪いことが起きる年」としての意味がなかったからだと思われます。
生活が豊かになり、人生を楽しもうとした時代になって「厄年」が脚光を浴びてきます。
これは、「天中殺」や血液型占い、水子供養などの霊感商法も、だいたい1970年あたりに出てきていることを考えますと、「脅せば金になる」という、人間の弱みにつけこんだ商法に思えて仕方ありません。
ただ、人間というものは、どんな状況においても、不安を抱えながら生きています。
厄年の習俗事態は古いものであり、男42歳、女33歳の大厄は江戸時代に生まれた考え方です。「死に」で42歳、「散々」で33歳という語呂合わせによるものだったようです。
最近になって生まれたものではありません。多くの人々が厄年を気にするようになったのは、最近のことですが・・。
民謡や童謡に出てくるような生活サイクルであった時代には、「厄年」は生活の風習などの中で自然に「厄払い」をしていたようです。
季節に絡んだ習俗や正月を迎える行事など、人生をリセット状態にしたり、けじめをつけることで「厄年」を恐怖していなかったようなのです。
ところが、日本人のライフサイクルはこの30年で大きく変化してきました。女性に関しては、この10〜15年でもっと大きく変化してきているのではないでしょうか。
田舎の生活に縁遠い、季節感を感じることの少ない都会の人ほど厄年を気にする傾向があります。それは生活の中で「厄年」を祓えないからです。
たとえば正月行事は根本的に古い年の厄を払い、新しい年を迎えるために行われるものでした。村に生きる人々は、自動的に厄払いをしていたことになります。
また、特に意識しなくても年中行事には厄払いの意味があり、特別のことが起こらないかぎり、厄払いをしてもらう必要はなかったのです。
都市に生きることで、地域社会のしがらみから解放されました。
そして、年中行事の義務からも解放されました。しかし、自由になった反面、生活におけるリズムを失いました。
年中行事が作り出していた1年のリズムを喪失。自然と離れた生活は季節の移り変わりはテレビコマーシャルでしか体験出来なくなってきます。
夏はサーフィン、秋はキャンブ、冬はスキー・・これらに、バレンタイン、ホワイト・デー、ひな祭りというより人形の販売合戦、とどめはキリスト教のクリスマスです。
日本の習俗とかけ離れた都会の生活では、季節感どころか、人生の「季節」も感じなくなってきました。
習俗に守られた地方では恐がらないことも、漠然とした不安をエサにして、都会では商売に成長します。そして、都会は「発信力」があるのです。
地方は、心配する必要がないにもかかわらず、都会の「発信力」に左右されることになりました。
厄年は都市的不安と深く結びついています。
それでは、厄年という習俗を私たちはどのように捉え、いかにして楽しい生活を送るための智恵やきっかけに変換出来るでしょうか。
「厄年」を人生の転機として考える年にする、自分の人生を振り返る年にする、人生のリフレッシュの年とする、不得手なことの克服の年とする、地域とのつな がりを再構築する、健康面を認識して生活を見直してみる、家族のあり方を考える、初心に返る、場合によってはリセットをしてしまえるのが「厄年」です。
厄年は、私たちが人生の挑戦者かどうかを判定するチャンスと考えるべきではないでしょうか。
人生にチャレンジしていれば、問題が途切れることはありませんし、トラブルの連続となります。しかし、それを恐れてはいけないのです。
チャレンジャーとして再認識するのが「厄年」だと思いたいではありませんか。
人の役に立てる年齢になったと考えてみるのも良いことですね。
私たちは、なんらかのかたちで、他人に助けられ、支えられて生きています。
その支えてもらっている周囲や社会に対して、どのような貢献ができるのかを考えてみることが出来るのが「厄年」ではないでしょうか。